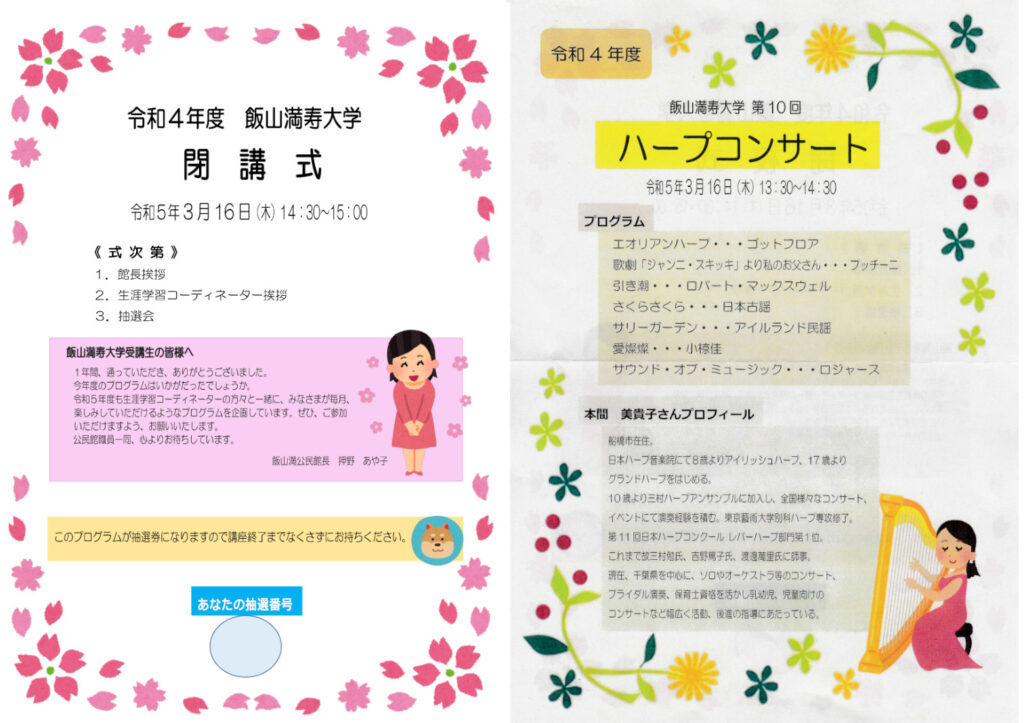日時:2025年11月21日(金) 09:30~12:30
講師:平山 恭子氏(学芸員)
参加者:20名+飯山満公民館・コーディネーター計4名
コース:高輪ゲートウェイ駅(集合)➡築堤跡➡柴田錬三郎旧居跡➡高輪館➡高輪消防署二本榎出張所➡明治学院大学➡瑞聖寺➡港区立郷土歴史館(解散)
小春日和の1日、天気に恵まれ高輪から白金台へ歴史ある建物探訪を実施した。


【高輪ゲートウェイ駅】
古来より「高輪大木戸」として賑わいをみせたこの地に、東京五輪に併せて山手線30番目の新駅として2020年3月14日に開業した。駅舎は駅を中心とする21世紀のアーバンデザインのモデルケースとし「駅まち一体」のテーマを基に設計され、国立競技場などで実績のある隈研吾氏がデザインを担当した。折り紙をモチーフとした大屋根や障子をイメージさせる膜と木を使用することで日本的価値を体験でき、海と陸を繋ぐ東京の新しいゲートを期待してこの駅名となった。
【柴田錬三郎旧居跡】
代表作の「眠狂四郎」シリーズなどで知られる歴史・時代小説の大家の旧居跡。外壁と住居土蔵が統一されたデザインで普請の高さが伺える。(非公開のため外観のみ)
【高輪館】
1925年(大正14年)に旧朝吹常吉邸(三井財閥幹部)の私邸として建てられ、その後旧加賀藩前田邸宅、東芝山口記念館(東芝グループの迎賓館)を経て現在は高輪館と称して日本テレビの所有である。(非公開のため外観のみ)


【高輪消防署二本榎出張所】
昭和初期の面影を色濃く残す高輪消防署二本榎出張所は1933年(昭和8年)に建設され、東京都選定歴史的建造物に指定されているが、東京都消防庁内で活動する最古の消防署出張所である。竣工当時は周囲に高い建造物がなく、東京湾からも見えたため「岸壁上の灯台」「海原を行く軍艦」と呼ばれていた。昭和16年から39年まで国産消防自動車の第1号車両が活躍し、現在も署員により毎日磨かれた状態で展示されている。上述の通り現役の消防署であるが、内部の見学は可能である。


【明治学院大学】
横浜開港時の1859年(安政6年)に来日したアメリカ人宣教医ヘボン博士は医療の施しに加えヘボン式ローマ字を考案し、本格的な和英・英和辞書を編集し聖書の日本語訳を完成させた。1887年(明治20年)白金に明治学院を開学する。当時の外国人居留地だった築地から白金は遠いため、宣教師の住居としてインブリー館(日本での洋式住宅の変遷を知る貴重な建造物)を建設し、1890年(明治23年)に神学部の教室として明治学院記念館を、1916年(大正5年)に礼拝堂(チャペル)が建てられ、今回は特別にチャペル内部の見学が許された。
チャペルはイギリスゴシック様式で、窓のステンドグラスは黄色の十字架の形であり、伝統工法により制作された日本最初のパイプオルガンが設置されている。
当初の建物から増築し、現在は空から見ると建物自体が十字架の形で、インブリー館、記念館と共に2002年(平成14年)に東京都の「特に景観上重要な歴史的建造物等」に指定された。今回はチャペルに加え、記念館と資料館の見学を行った。


【瑞聖寺(ずいしょうじ)】
1670年(寛文10年)に創建され、江戸時代には江戸黄ばく宗(臨済宗、曹洞宗と並ぶ日本三禅宗のひとつ)の中心寺院で「一山之役寺」と呼ばれていた。現在の本堂(大雄宝殿)は高輪下馬将軍として名高い薩摩藩主 島津重豪により1752年(宝暦7年)に再建された。この本堂及び通用門は1992年(平成14年)に国の重要文化財に指定された。瑞聖寺は2020年(令和2年)に創建350年を迎えた記念事業の一環に、老朽化した庫裏(くり:住職の居間や台所)の改装を隈研吾氏に依頼し、中央の水盤を囲むようにコの字型に設計され、庫裏から水鏡の水面に写る大雄宝殿の美しい姿は必見。(但し当日は水鏡の清掃中のためその姿が見られず残念)
【港区立郷土歴史館】
歴史的建造物を活用して港区の自然・歴史・文化を知り交流の拠点として2018年(平成30年)に開館。この建物の原型は1938年(昭和13年)に竣工した旧公衆衛生院である。構造は鉄骨・鉄筋コンクリート造り、壁面をスクラッチタイルで覆われたゴシック調の外観は隣接する東京大学医科学研究所と対の建物であり、本郷の東京大学安田講堂に良く似た設計である。今回は中央ホール、旧講堂(NHK朝ドラの「虎に翼」のロケ場所で昭和初期の学校建築)、旧院長室、旧食堂などを見学した。